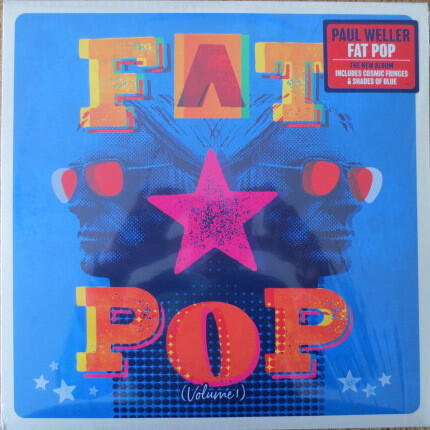ブラーは、マンチェスタームーブメントの末端からデビューし、60年代から90年代までのUKロックの歴史を包括した「LIFE三部作」でブリットポップの中心としてシーンで輝きました。その後、USオルタナ志向が強まった傑作「BLUR」、外部のプロデューサーの力を借りデーモンの個性が強く出た2枚を発表し解散。解散後も何度か再結成しツアーを行い、ファンへの手紙のような2作(結構な力作)を届けてくれています。
個人的には、高校、大学の多感な時期に「LIFE三部作」がリリースされたこともあり、音楽のみならずファッション等も含めて、常に憧れの存在です。英国=BLURのイメージがあります。別の世代にとってのBEATLES、JAMあたりに近い感じ。
UKロックの至宝、ブラーのアルバムをレビューしてみました。
- Blur – Leisure
- Blur – Modern Life Is Rubbish
- Blur – Parklife
- Blur – The Great Escape
- Blur – Blur
- Blur – 13
- Blur – Think Tank
- Blur – The Magic Whip
- Blur – The Ballad Of Darren
- アルバムランキング
Blur – Leisure

91年発表の1stアルバム。デーモン・アルバーンは68年生まれなので、当時23歳ぐらい。
ブームのピークを迎えたマンチェスタームーヴメント(ムーブメントの中心にいたプライマルがスクリーマデリカを発表)とシューゲイザー(マイブラがラブレスを発表)の間の子のようなサウンドで、バンド名通り、はっきりしない曖昧な感じのプロダクションだ。メロディ的には、今に至るフック満載のデーモン節を聴くことができる。ただ、マンチェをなぞるもグルーヴの無いリズムと、この時点では無個性なグレアムのギターを中心に、全体的には緩く締まらない。当時、このバンドが30年以上も愛される国民的バンドになることを予見した人はどれぐらいいただろうか。
曲単位では、全英43位まで上がったデビューシングル「She's So High」、セカンド以降に繋がる感じで完成度の高い「There's No Other Way」 (最高位8位)、3RDシングル「Bang」トレインスポッティングのサントラに収録された「Sing」等、当時のクラブシーンの影響をポップに昇華させた良い曲がいくつかある。どの曲もギンギンにサイケで、この露骨にドラッギーな感じもこの作品の特徴だ。
改めて聴くと、以前より2nd以降との関連性を見出すことができるし、90年代に聴いていた頃よりは悪くない。ただ、デーモンのこの作品への評価「awful」程は悪くはないが、この後の傑作に比べると凡作だ。
Blur – Modern Life Is Rubbish

93年発表の2nd。
借金返済のためのアメリカツアーや、SUEDEとの比較で疲弊したデーモンが自らのルーツに立ち返った一枚。ブリットポップの幕開けを飾る「英国三部作」の初作だ。
アルバムは当初XTCのアンディ・パートリッジが関わっていたが、うまくいかず、1stと同様にスティーブン・ストリートが指揮することになった。
キンクス、スモール・フェイセス等の60年代UKロックを原材料に、ニューウェイヴや前作からの流れのドラッギーなサウンドで味付けし、デーモンならではのコード進行やメロディで90年代にリモデルした。
前作のクラブ系のドラッギーなイメージから、クリーンなモッズにチェンジした「For Tomorrow」のMV。当時高校生だった自分にもこのMVは大きな影響を与えた。モッズになりたい、BLURみたいになりたいと思った。ジーザス・ジョーンズやEMFは聴いていたが、このバンドからUKロックにどっぷりハマった。
小洒落たギターのイントロがアルバムの成功を確信させる、捻くれながらもポップなメロディの「For Tomorrow」、「Advert」「Blue Jeans」「Chemical World」「Sunday Sunday」ポップな名曲揃いだ。この後の、ちょっとデーモン的なマーケティングが入ったソングライティングより、まだ若々しい自然に出来た感じが格別。他のアルバムとは明確に差別化できる。
時代を感じさせる音だが、それだけに聴きまくっていた10代の頃をはっきりと思い出させてくれる。自分の中では、ブラーやブリットポップの枠を越えオールタイムフェイバリットアルバムの上位に入る大名盤だ。
Blur – Parklife

94年発表の3RD。ブラーの代表作。
リリースに先駆けてシングルカットされた「Girls & Boys」に象徴されるように、ビートは多様化し、メロディは前作の60〜70年代ポップから80年代に、ギターは同じくニューウェイヴやパンクに近づき、初期のマンチェやシューゲイザーな感じは一層された。全体的なトーンは、シド・バレットやジュリアン・コープの影響を感じるドラッギーな音感覚だ。
アルバムに先駆けてリリースされたディスコポップチューン「Girls & Boys」は、全英5位にランクインし、この時点でバンド最大のヒット曲となった。「End Of A Century 」はキンクスと、ストロベリーフィールズとペニー・レインの時期のビートルズが合体したようなブリットポップど真ん中のシンガロングソング。アルバムタイトル曲の「Parklife」は、モッズ映画「さらば青春の光」のフィル・ダニエルズをゲストに、中期スモール・フェイセズっぽいメロディと印象的なギターが楽しいバンドを代表する曲で全英10位のヒット。スモール・フェイセズっぽい「Far Out」がフェイドアウトし鳴り出すストリングスが最高な「To The End」はステレオラブのレティシア・サディエのフランス語をフィーチャーした映画っぽい曲で16位まで上がった。
デーモンの声は、キャリアの中で最も怠惰でクールに聴こえる。聞き手を小馬鹿にしているレベル。アレックスの立体感のあるベースと、グレアムの局面を変えるギターが、その「怠惰」を切り裂き、元々アルバム・タイトルとなる予定でもあった「ロンドン」の高揚感・緊張感を生み出している。
怠惰とニューウェイブ・パンクの緊張感の対比がブリットポップのプロトタイプと言える。「怠惰」を打ち破るものが、それぞれのバンドにあり、それぞれの特徴となっていた。この時期のブラーはデーモンのフックに富んだメロディ、グレアムのギター、アレックスのベースであり、例えばオアシスでのそれはビートルズへの盲目的な愛だった。
Blur – The Great Escape

95年発表の4作目。全英1位の大ヒットアルバム。
ブリットポップ最盛期で、マスメディアはブラー対オアシスの構図作りに必死だった。このアルバムからの1stシングル「Country House」とOASISの「Roll With It」が95年の8月20日、同日にリリースされ、チャート1位を巡り対決はクライマックスを迎えた。結果はマーケティングに秀でたブラーの勝利。曲の出来も「Country House」の方が良かったと思うが、あまりにバカバカしいMVと、その後のオアシスの名曲ラッシュにブラーは後塵を拝するようになる。ブリットポップバブルも急激にしぼんでいった。
狂騒の中でリリースされ、ブラーの失速とともに評価が大きく下がった残念なアルバムで、デーモンも「レジャー」とこの作品をできの悪いレコードと評しているが、実はバンドのキャリアの中で最もポップなメロディーと、躁鬱のバランスが整ったサウンドプロダクションを誇る完成度の高い作品だ。
リードシングル「Country House」はコンパクトにまとまった英国箱庭のようなポップソングで、madnessからCSN&Y、クイーン等走馬灯のようにロックの亡霊が駆け巡る派手な曲。「Best Days」はややドラッギーな沈んだ感じのトーンだが、美しいメロディが印象的な個人的にはアルバムで一番好きな曲。前作からの流れを汲むモリッシーもお気に入りのナンバー「Charmless Man」はトイレの落書きをヒントに作られ全英5位。「The Universal」はスモールフェイスにも同じタイトルの曲があるが曲調は全く関係なく、前作の「To The End」の延長のような、ストリングスを全面に出した映画的な曲で、「2001年宇宙の旅」「時計じかけのオレンジ」をリスペクトしたMVも話題になり全英5位まで上がった。
ブリットポップの表看板といえる「ライフ三部作」はこれで完結し、次のアルバムからバンドは別のモードに入る。
Blur – Blur

97年発表の5thアルバム。逆境の中で全英1位、ビルボードでも61位まで上がり、世界的な成功を収めた。狭い世界に閉じ込められそうになっていたバンドを、次のステージに押し上げた。
グレアムのUSインディー趣味をバンドが共有。サウンドプロダクションが一新された。乱痴気騒ぎのパーティー三昧だったバンドが、リスナーと同じストリートに戻ってきたような、ゴツゴツしたリアルな音がかっこいい。
メロディーはベックやペイブメントの影響も強いが、分解すればUK的で、例えばリードシングル「Beetlebum」はビートルズ、それもジョン・レノン的なサイケソングだ。
ジャムで曲を固めたサウンドが素晴らしい。バンドの創造力を強く感じられる。サウンドを引っ張るのはグレアムのささくれだったギターの音だ。USオルタナ・インディーの影響を受けてながらアイデアに富んでいる一方、怠惰でクールで余計なフレーズを引いていないUKっぽいパンク・ニュー・ウェイブなクールさを併せ持っている。また、全体がシンプルになったことで、アレックスのベースもこれまでの作品以上に存在感を発揮、表情豊かにウネリまくってメロディ面でアルバムに色を加えている。
「Beetlebum」はタイトル通りビートルズの色が露骨に出たサイケデリックなナンバーでダウナー系のドラッグの強い影響を感じさせる。シド・バレットやジョン・レノンのソロ作にも通じるパーソナルな世界から、一気に宇宙までぶっ飛ぶような展開が素晴らしい。MVも世界観を明確に表している。全英1位となりアルバムの成功を確実にした。
グランジをパロディにしたような「Song 2」は世界的に大ヒットしたブラーの代名詞的なオルタナ・パンク曲で、子供でも一発で入り込めるメロディと、グレアムのギター、アレックスの唸るベース、イントロからブチかますデイブのドラムが渾然一体となって襲いかかる感じが圧巻で全英2位。「On Your Own」は全英5位のヒップホップ+オルタナ的な曲で、デーモンは「ゴリラズの曲」と言っている。M.O.R.はデビッド・ボウイの「Fantastic Voyage」「Boys Keep Swinging」の実験に付き合ったポップなパンクナンバーで、ここでもグレアムのギターが光っている。「You're So Great」はグレアムが独りで作った弾き語り曲で、素朴な音がかっこよく、ライブでは非常に盛り上がった。
グレアムはこのアルバムを最高傑作の一つと評価している。時代やジャンルを越えて楽しめる傑作アルバムだ。
Blur – 13

99年発表の6枚目。4作連続で全英1位を獲得した。
デーモンが長年のパートナージャスティン・フリッシュマンと破局し、その影響でアルバム全体のトーンが暗く、これまでのポップでクールなイメージとは異なるテイストの作品になっている。デーモンのキャリアの中でも最も自閉的なアルバムだ。
この時期はバンドメンバーの関係性も悪化していた。アルバムタイトルの「13」は、デーモンとその他3名を示すと言われることもある。
プロデューサーは、デビューから前作まで担当したスティーヴン・ストリートから、マドンナ等のプロデュースで知られるウィリアム・オービットに変わった。
アルバム・ジャケットはグレアムが書いた油絵だ。
ジャスティンとの破局を歌った「Tender」は、ゴスペルっぽいサウンドと、グレアムとデーモンの掛け合いが素晴らしい曲で、全英2位まで上がった。傷心のデーモンをグレアムを中心とするバンドメンバーが励ましているように聴こえる。
牛乳パック君がコミカルに動き回るMVが印象的なグレアムをフィーチャーした「Coffee & TV」は、アルコール依存症に悩むコクソンが飲酒をやめてコーヒーを飲みながらテレビを見ているリラックスな状況で書かれた。オルタナ感満載のギターソロがくそかっこいい。この冴えた2曲がアルバムの顔だ。
アルバムの後半は美しいメロディとゆったりとしたサウンドがかっこいい「Mellow Song」「No Distance Left To Run」が締めている。
アルバム全体として、曲は小粒で暗く、ウィリアム・オービットの色はほとんど感じられず、名盤揃いのブラーの中では中途半端な出来栄えだ。名盤揃いの99年にあって、至って地味な作品だ。
Blur – Think Tank

ゴリラズの活動を挟み03年発表した、実施的なラストアルバム。グレアムはほとんど参加しておらず、デーモンのソロプロジェクト的な色合いが強い。
前作の反動からか、デーモンはアルバムをコマーシャルなものにしようと考えた。結果としてノーマン・クックを含む複数のプロデューサーが絡み、「愛と政治」をコンセプト(アフガニスタン侵攻に反対)にしながらも、練られたメロディ、多種多様なリズムと素晴らしいサウンドプロダクションが同居した、安定感のある傑作に仕上がった。
冒頭4曲が非常に素晴らしい。イントロからアルバムを象徴するファンクネスが炸裂する「Ambulance」、シンプルなメロディと奥行きのあるサウンドがかっこいい 「Out Of Time」 、ノーマン・クックらしいパーティチューン「Crazy Beat」、優しげなメロディとサウンドがある意味新境地でずっと聴き続けられる「 Good Song」、後半も、儚げなピアノの音が印象的「Sweet Song」、グレアムがギターで唯一存在感を示す美しい別れの曲「Battery In Your Leg」など佳曲揃いだ。
リリース当時、ジョージ・マイケルの「FAITH」みたいだと思った。それぐらいギターバンドとしての色は薄まり、ポップでありながらソフトなファンクっぽさがクールで、デビュー当時のバンドの姿は遠くに消えてしまった。ただ、それはデーモンとしてごく自然な変化で、その後の作品に繋がるデーモンのキャリアの中で重要な1枚だ。
尖ったサウンドとポップさのバランスが取れた非常に「よくできた」アルバムだ。BLURの作品の中でも3番目ぐらいに好きな作品で、この方向性あと2~3枚出してほしかった。
アルバムジャケットはバンクシーによるもので普通にかっこいい。
Blur – The Magic Whip

再結成後の15年に発表された作品。日本ツアーが中止になった後、香港で作られた。
シンクタンクのような作り込んだ感じは無いが、リズムに進化が感じられ、デーモンの歌声もなかなか良い。
ビルボードでバンド史上最高位の24位まで上がった。プロデューサーは初期にブラーを支えたスティーブン・ストリート。
たまに聴くと発見がある。
Blur – The Ballad Of Darren

23年発表。タイトルの「ダレン」はデーモンのボディガードの名前。
プロデュースはシミアン・モバイル・ディスコのジェイムズ・フォードで、バンド・サウンドを活かしたギターロックアルバムになっている。
特に凝ったアレンジの曲もないが、バンドが楽しそうに演奏しているのが伝わってくる嬉しい作品だ。
たまに届く学生時代の友達からのLINEみたいな感じだ。
アルバムランキング

個人的なランキング。
9位 The Magic Whip
8位 Leisure
7位 13
6位 The Ballad Of Darren
5位 The Great Escape
4位 Blur
3位 Parklife
2位 Think Tank
1位 Modern Life Is Rubbish